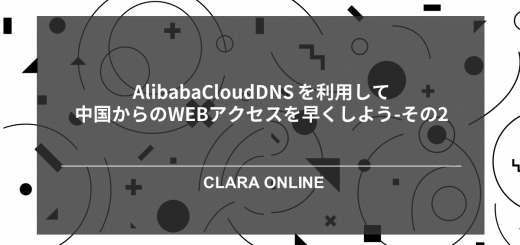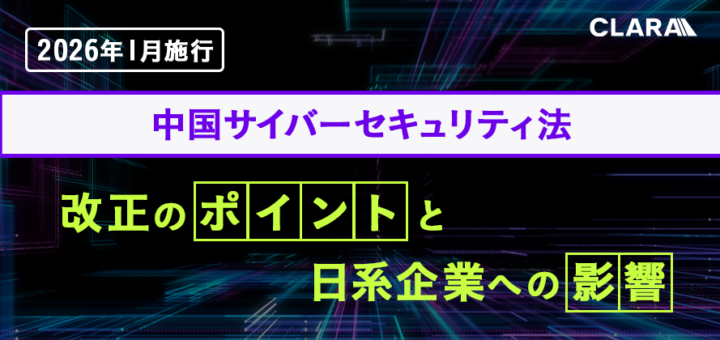
【2026年1月施行】中国サイバーセキュリティ法 改正のポイントと日系企業への影響
こんにちは!クララのマーケティングチームです。
2025年10月28日に採択された「中華人民共和国サイバーセキュリティ法(以下、中国サイバーセキュリティ法)」の改正が、2026年1月1日より施行されます。
本改正は、AIやデータ安全をめぐるリスクの高まりを背景に、法令遵守(コンプライアンス)リスクと運用コストを大幅に引き上げる内容となっています。
特に注目すべきは、罰則の劇的な強化と、データ管理・インフラ調達に対する国家安全保障上の監督強化です。
この記事では、改正の主要ポイントと、日系企業への具体的な影響をわかりやすく整理します。
2025年10月28日に採択された「中華人民共和国サイバーセキュリティ法(以下、中国サイバーセキュリティ法)」の改正が、2026年1月1日より施行されます。
今回の改正は、AIやデータ安全をめぐる環境変化に対応するもので、企業のコンプライアンスリスクや運用コストを一段と引き上げる内容です。
特に注目すべきは、罰則の劇的な強化と、データ管理・インフラ調達に対する国家安全保障上の監督強化です。
つまり、中国でITやクラウドを活用する企業にとって、「これまで通りの管理」では通用しない時代に入る、ということですね。
この記事では、改正のポイントと日系企業が押さえておくべき影響をわかりやすく整理します。
この記事の目次
罰則が10倍に:企業・個人双方への法的リスクが拡大
まず最も分かりやすい変化は、罰金の上限が10倍(最大1,000万元)に引き上げられた点です。
これまでのように“是正すれば済む”レベルではなく、違反が事業継続に直結するリスクへと変化しました。
企業への罰金強化
- 特別重大な結果(例:重要情報インフラの停止、大規模なデータ漏洩など)を招いた場合、最大1,000万元(約2億円超)の罰金。
- 一般的なセキュリティ義務違反でも、拒否や放置があれば重い処罰対象となります。
つまり、従来の「行政指導レベル」から、「経営リスクレベル」へと格上げされた、ということです。
個人責任の強化
違反行為に関与した管理者や担当者個人への罰金も最大100万元に。
これにより、企業だけでなく、現場や責任者にも直接的な法的責任が及びます。
一言でいえば、「組織で守る」だけでなく「個人も守られる体制づくり」が求められる時代です。
行政処分と信用影響
さらに、罰金だけでなく、業務停止・営業許可証の取り消し・信用リスト登録など、行政・信用上のペナルティも明文化されました。
信用リストに入ると公共入札や許認可更新にも影響します。
つまり、“一度の違反が将来のビジネスチャンスを失わせる”可能性があるということです。
データ・AI・インフラ管理における新たな義務とコスト増加
個人情報・データ管理の厳格化
改正では、個人情報保護法や民法典との整合性が明記され、企業が従うべきルールがより明確になりました。
これにより、実質的に企業は次の三法を一体で運用する必要があります。
- 中国サイバーセキュリティ法
- データ安全法
- 個人情報保護法
どれか1つを守ればよい、という時代はもう終わりです。
「3法一体」で管理体制を組むことが、中国市場での前提条件になります。
越境データ移転の扱い
- 【CII運営者の場合】国外移転には国家の安全評価(セキュリティレビュー)が必須(第39条)。
- 【非CIIの場合】個人情報保護法に基づき、データの性質に応じて以下のいずれかを実施します。
-
- 国家当局の安全評価
-
- 標準契約(SCC)締結
- 標準契約(SCC)締結
-
- 個人情報保護認証の取得
- 個人情報保護認証の取得
言い換えれば、「CIIでなくても越境データは自由に出せない」ということです。
企業は自社がどの分類に属するのかを明確にし、データの流れ(収集〜保存〜転送)を設計段階で管理する必要があります。
AIに関する監督強化(新第20条)
新しく追加されたAI条項では、AI技術の発展支援と同時に、倫理・安全・リスク管理の強化が明記されました。
- AI基礎理論やアルゴリズムの研究支援
- AI倫理規範や安全監督の整備
- AIを活用したセキュリティ対策の推進
つまり、「AIは推進するが、制御できなければリスク要因にもなる」という立場を明確にした形です。
今後は、AIを組み込む製品・システムにも、安全評価や倫理レビューが求められる可能性があります。
ネットワーク製品調達の厳格化(新第63条)
ネットワーク製品やセキュリティ機器についても、安全認証・検査合格の義務化が導入されました。
認証を受けずに販売・利用した場合、売上の5倍の罰金、場合によっては営業停止まで及びます。
特にCII運営者が製品を導入する場合、国家安全審査(第37条)を経る必要があります。
つまり、今後は“どの製品を使うか”も企業のリスク管理の一部になる、ということですね。
海外企業も対象に:域外制裁条項の新設
改正第77条では、中国国外の企業や個人が「中国のサイバー安全を害した」と判断された場合、財産凍結や制裁措置を取れることが明記されました。
これは、中国国外で行った行為でも、中国のネット空間に影響すれば処罰対象になり得るということです。
日系企業であっても、中国ユーザー向けサービスの提供や通信経路の設計が、国家安全と見なされれば制裁対象になる可能性があります。
つまり、「中国国内に拠点がなくても無関係ではいられない」、そうした時代の到来です。
地政学的な観点からも、各国法規の整合性やガバナンスの再設計が求められます。
日系企業が取るべき5つの対応
今回の改正は、単に罰則が厳しくなったという話ではなく、中国で事業を行う全ての企業に求められる「運用の再設計」を意味します。
① コンプライアンス体制の再構築
- 中国サイバーセキュリティ法・データ安全法・個人情報保護法の三法に対応した統合監査を実施。
- 違反時の潜在コストが大幅に増したため、セキュリティ・法務体制の強化が急務です。
→ つまり、「守るためのコスト」が「失うリスク」より小さいうちに対策を取るべき、ということです。
② CII該当性の再評価
- 自社がCII指定対象(公共、製造、交通、金融など)に含まれるかを定期確認。
- CII運営者としての義務(専任担当配置、年次検査、報告など)に備える。
→ 業種やデータの扱い次第では、思わぬ形でCII対象になる可能性もあります。
③ データローカライゼーションの徹底
- 中国国内で生成・収集されるデータを特定し、保存・転送経路を明確化。
- 越境移転時は安全評価、標準契約(SCC)、または個人情報保護認証のいずれかを早期申請。
→ データは「国境を越える資産」から「国の管理対象」になりつつあります。
④ サプライチェーン監査
- 調達先・ベンダーが中国法令に基づく認証を取得しているかを確認。
- 契約書に「中国法令適合条項」を盛り込む。
→ 製品やサービスを“買う側”にも、法令理解が求められる時代です。
⑤ インシデント対応体制の整備
- 中国当局への報告義務(ネットワーク安全事件応急予案など関連規定に基づく報告時間)を想定し、緊急対応フローを策定。
- 「初犯・軽微・迅速報告」で罰則軽減が可能になるため、自己申告ルールの整備を。
→ トラブルを「起こさない」だけでなく、「正しく報告できること」が企業防衛になります。
まとめ:中国サイバーセキュリティ法改正は「統治法」への進化
2025年の改正は、単なる技術法の改定ではなく、中国の国家安全法体系の中でサイバー空間を包括的に統治する法制度へと進化したものです。
つまり、「IT管理」はもはや“システムの話”ではなく、“経営と安全保障の話”になったということです。
AI、データ、クラウド、ネットワークのすべてが規制の射程に入り、企業はそれらを包括的に管理する必要があります。
クララでは、中国市場における制度変化と実務の両面から、お客様の安全で持続的な運用をサポートしています。
中国でのクラウド・Web・ネットワーク構築についてご相談がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。