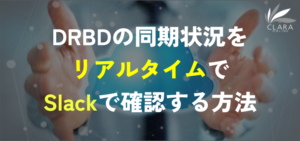2020年12月3日、クララ株式会社主催によるオンラインビジネスカンファレンス「The Border 2020」が開催された。デジタル化が加速する中、技術や環境の変化に対応し、成長を実現するには何が必要か。本カンファレンスでは“Border”(既成概念・国境)をテーマに、それを壊し、超えるためのDXや組織変革、コスト・運用負荷削減、働き方改革、中国市場に関するプログラムなど、さまざまな講演やセッションが展開された。
その中で本記事では、『アフターデジタル』の著者で、株式会社ビービット 東アジア営業責任者の藤井 保文氏と、クララ株式会社 代表取締役社長の家本 賢太郎氏による「【特別対談】Borderを超える力~事業成長に必要な思考~」の模様を紹介しよう。
デジタル化の真の意味や今後のオンラインとリアル世界の関係を鋭く突いて大きな話題を呼んだ『アフターデジタル』シリーズの著者である株式会社ビービットの藤井氏は、本カンファレンスにおいてまず基調講演「【基調講演】アフターデジタル時代のビジネス機会、新たな視点」を行った。基調講演では、デジタルとリアルの境界がなくなった時代において“Border”を超える事業のヒントとして、国内外の事例も紹介された。
その後に行われた特別対談では、まず家本氏が藤井氏の基調講演について「DXやアフターコロナにおけるオンラインとオフラインを融合させた取り組みには、これまでの事業を否定するのではなく、従来の良さを残しながら新たな挑戦を図っていくことが重要だという話が、きわめて納得感が強かったですね。新しいことを始めるときは否定から入ってしまいがちですが、そうではないということに共感できました」と感想を述べた。
対して藤井氏は「ビービットがDXを支援している企業でも、新しいことをやらなければという意思がほとばしりすぎて、『以前のままではダメだ』となってしまうところが多いのが実情です。ダメだと言われた現業部門からは当然、反発が生まれますから、これでは社員みんなの意思が統合されていきません」と応じた
家本氏は、同社の事業にて北京で仕事をすることが多かったというが、同じく中国関連の仕事に携わることの多い藤井氏とはまだリアルの場で会ったことがないという。『アフターデジタル』を読んだのも中国と往復する飛行機の中だったとのことだが、家本氏はこの本から自社の事業の参考にしたケースがあったと話した。
「クララのグループに中古スポーツ用自転車買取・販売の『バイチャリ』という事業があります。もともとはリアルなお店があり、あとからECも始めたのですが、結果でいうと現在、売上の約3分の1はECで実現しているんです。僕は最初、デジタル化するならオールECにして、リアルな店舗はやめるべきなのかと悩んでいました。一方で、自転車も最後の最後は、乗り心地や色合いなど実際に触ってみないとわからないことがあるので、やっぱりリアルのお店も必要になる。すると、リアル店舗とECをどう組み合わせればいいかを考えるということになります。結果的にいまECサイトは商品カタログの役割を持っていて、そのままECで売れるケースも3分の1あるわけですが、多くはECを見てからリアルのお店にくるという導線がはっきりとした形で生まれ、そこにKPIを設定できることもわかってきました。これは実は『アフターデジタル』を読んで発見したことでして、藤井さんには本当に感謝しています」
そう話した家本氏は、そもそも中国でECの動きを見て「ECはエンターテインメントだと思った」という。ECは単にデジタルで商品を買うことではなく、ECという購買行動自体やECサイトで商品を探すこと自体が楽しみであると感じ、そのイメージをベースにECとリアルの組み合わせ方を考えているタイミングで藤井氏の著書に出会ったと語った。
藤井氏はそれを聞いて、日本企業の傾向について次のように続けた。
「レガシーな企業であればあるほど、デジタル化といわれるとすべてにおいてデジタルなことをやらなければいけないと思いがちのようで、ECをやるならECだけで完結したほうがいいと考えてしまいます。ハイタッチ、ロータッチ、テックタッチという分け方がありますが、デジタルと聞いた日本企業の多くはテックタッチだけをやればいいと考えがちだということですね。しかしながら、これまでの日本企業の強みはむしろハイタッチ、ロータッチの部分。ですので、すべてをデジタルでと考えず、いかにその強みをテックタッチとつなげてユーザー体験を良くしていくか、という話なのだと思います。要するに、ユーザー体験起点で考えれば良いということ。同様に、アフターデジタルというとデジタル側に移行しようというように聞こえるのですが、そもそもユーザーの立場からすれば、デジタルとリアルの区別などありません。だから、これについても同じく、ユーザー視点で考えようというだけの話なんです」
続けて家本氏は、今後日本企業はオンラインとリアルが重なる領域でどういった強みを発揮できるか、どうすればチャンスをつかめるのかと藤井氏に尋ねた。
藤井氏は次のように答えた。
「最近はプログラミングなしでもアプリを作れるようになるなど、技術がテンプレート化・パターン化してきました。この流れの中では、そうした技術を使ってどんな世界を作りたいのか、いわゆる世界観やその構想力のほうがよっぽど重要です。中国ではスマートシティがテンプレート化した結果、街の特徴や文化が失われてきており、むしろいまはそういったものをどう作り上げるかが重視されています。そこで最近は、くまモンのコンセプトを生み出した小山薫堂さんや、多彩な建築を手掛ける隈研吾さんなど、世界観を作るために日本の人を登用する動きが出ています。日本はまだまだ“クール・ジャパン”と言われるように構想力については世界のトップレベルですので、デジタルで最適化だ、効率化だといわれたからといって、その構想力のアドバンテージを捨てる必要などまったくありません。むしろ構想力は、今後、これまで以上に必要になるものだと私は考えています」
これを受けて家本氏は、こう話した。
「クララも、“HOW”つまりどのようにやるかを考えてしまうクセがあります。もちろん、それは当社の事業であり得意分野であるわけですが、これからは原点として、私たちはこういう未来を作りたい、なぜならこういうビジョンがあるからだ、という“WHY”の部分が大切だということがよくわかりました。消費者の共感を得るもの、ブランドとしての価値を生み出すものも、HOWではなくWHYです。日本企業もWHYをおそらくみんな持っているはずですが、これまでは言語化するのが得意ではなかったため、表現せずにきてしまったのかもしれません。一方で、日本のスタートアップをウォッチしていると、伸びているところはどこもビジョンがしっかりしています。そもそもそうしたビジョンが軸になっていなければ、出来上がる事業もブレてしまうことでしょう」
そのうえで、事業成長を目指すために企業独自のビジョンを表現すること、その前提として言語化が重要であることを再認識したと述べた。
最後に家本氏は、これからの日本企業に向けてのメッセージを藤井氏に求めた。
藤井氏は「世界観の構想力というものは、日本企業はもともと持っていましたし、いまでも強みであることは間違いありません。あとは、それをベースに新しい技術や環境をどう踏まえていくかが、事業を成長させ、世に広げていくためには必須です。日本全体がデジタル後進国と言われつつある中、日本の強みを活かす取り組みを社会として推進していくために、私もがんばりたいと思います」と話し、今後の日本企業の飛躍に期待を寄せた。